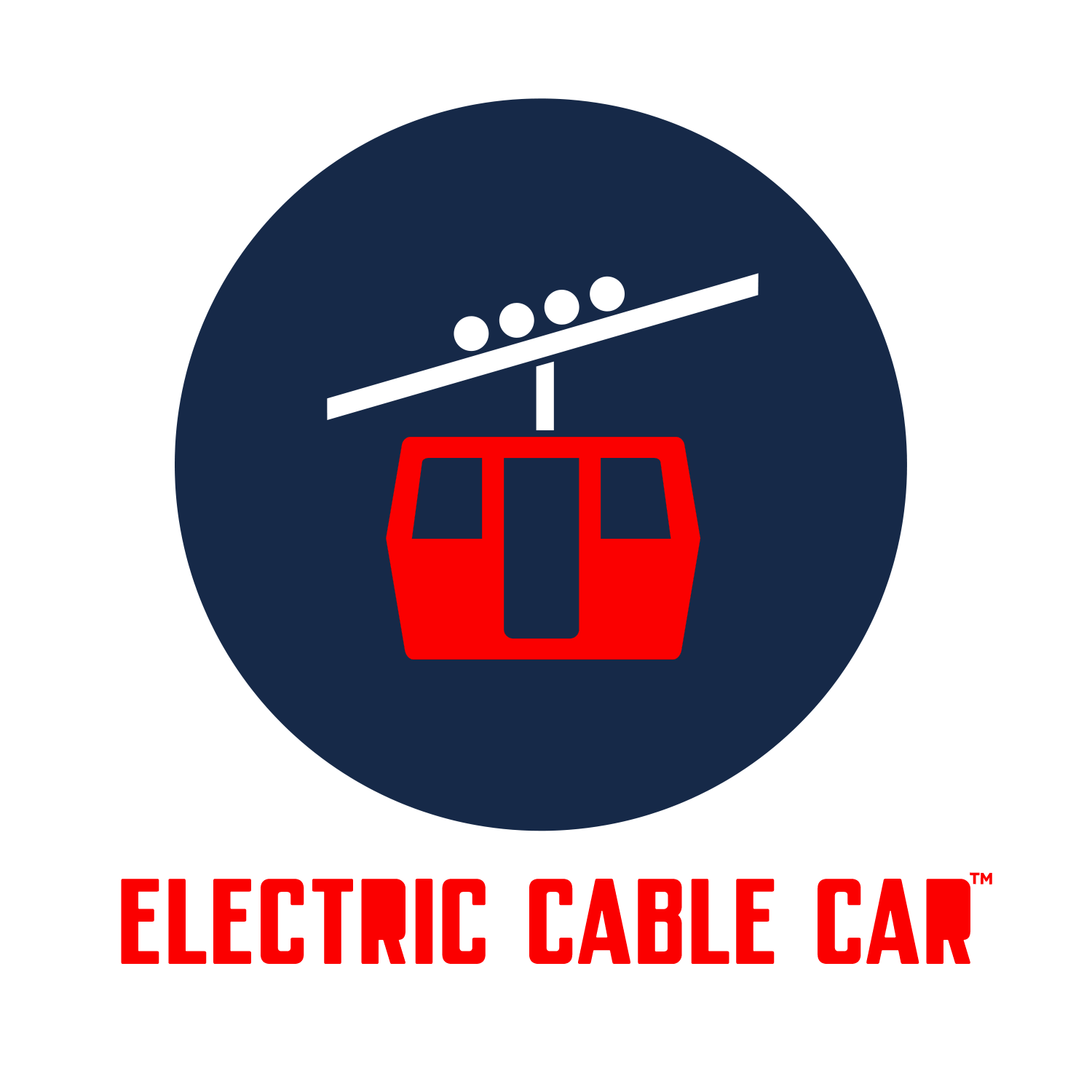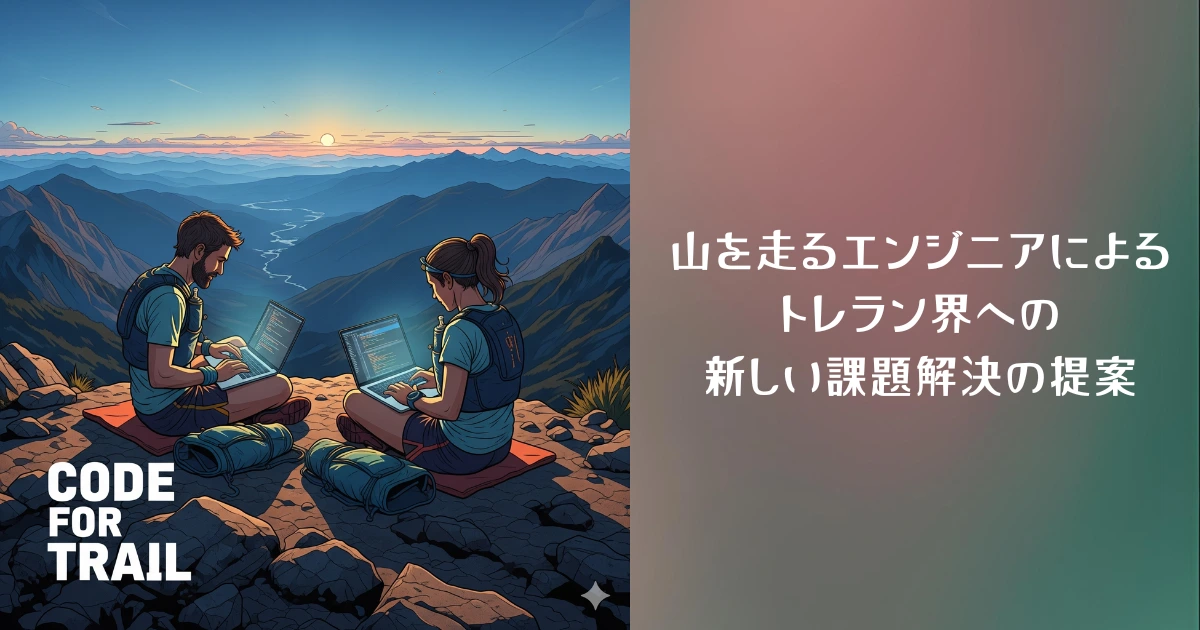GO ASIA TRAIL の堤です。
本日は、タイトルスポンサーについて。私の中で、「タイトルスポンサー」という言葉が一種のヘビーローテーションのような単語になっていて、いろいろ調べてみて、今回の記事を書いてます。
トレイルランニングの世界では、イベントの運営資金を確保し、ランナーや地域に還元するためのスポンサーシップが欠かせません。特に、タイトルスポンサー(または冠スポンサー)と呼ばれる形態は、大会名に企業名を冠する最上位のスポンサーシップで、多額の資金提供を通じて大会の質を向上させることが期待されます。この記事では、タイトルスポンサーの概要を説明し、日本と海外の事例を交えながら、その意義を探っていきます。
タイトルスポンサーとは?
タイトルスポンサーは、スポーツイベントの最高位のスポンサー形態です。例えば、大会名が「企業名 + 大会名」となることで、企業のブランド露出が最大化されます。これにより、大会主催者は多額のスポンサー料を受け取り、ランナーへの賞金増額、コース整備、地域活性化などに活用できます。
日本でのタイトルスポンサー:まだ珍しい形式
日本国内のトレイルランニング大会では、タイトルスポンサーを導入した事例はほとんどありません。多くの大会が実行委員会方式で運営されており、複数のスポンサーや自治体の支援で成り立っています。これは、都市型マラソン大会でも同様で、タイトルスポンサーを迎えるケースは稀です。
日本でタイトルスポンサーが少ない理由として、主に以下の点が挙げられます
- 伝統的な運営スタイルとして、自治体や地域コミュニティ主導の実行委員会方式が根付いており、単一の企業が大会名を冠する形を避けてるケースが多い。複数の企業や団体が協賛する形で資金を分散させるのが一般的です。
- トレイルランニングやマラソンイベントの多くが小規模または地域密着型であるため、メディア露出が少なく、企業にとってブランド露出の効果が限定的
大会主催者側は、タイトルスポンサー企業に不祥事が発生したときに、大会や地域名のブランドや信用失墜につながるので、日本では実行委員会方式で分散させる傾向にある。
これらの要因が絡み合い、タイトルスポンサーの導入が進みにくい状況を生んでいます。

しかし、最近の注目事例として、2026年2月に開催予定の京都マラソンが挙げられます。ここでは、任天堂がプラチナパートナー(として迎えられ、大会名に任天堂の代表的なゲーム作品である「マリオ」の40周年を記念して、「SUPER MARIO BROS. 40TH 京都マラソン」という名称で開催されることになった。
このコラボレーションでは、スーパーマリオをテーマにしたランナービブ(ゼッケン)やイベントが予定されている。ビブデザイン以外にも、おそらくノベルティやコース上での仕掛けも期待ができるかもしれません。
トレイルランニングではないものの、このような取り組みが今後、トレイルイベントにも波及するのではないかと期待している。
海外でのタイトルスポンサー:欧米・アジアで増加傾向
海外、特に欧米ではタイトルスポンサーを活用した大会名が一般的になってきています。近年、アジア地域でもこのトレンドが見られ、企業がブランド価値向上やマーケティングに積極的に投資しています。
一例として、2026年3月に台湾で開催予定のX-Trail Kenting by UTMBが挙げられます。このレースでは、HOKAがタイトルスポンサーとして関与し、UTMB World Series全体のプレミアパートナーとしてフットウェアやアパレルをサポートします。 HOKAは2024年からUTMBのタイトルスポンサーに昇格しており、グローバルなトレイルランニングコミュニティを活性化させる役割を果たしています。
また、アジアのトレイルランニングシーンでは、中国企業が積極的にタイトルスポンサーを務める事例も増えています。例えば、香港のHong Kong 100 Ultra Marathonでは、中国のスポーツブランドAnta(安踏)がタイトルスポンサーとして参加しており、2024年および今後の大会でブランド露出を強化しています。
また、ベトナムのVietnam Mountain Marathonでは、中国のアウトドアブランドKailas Fuga(カイラス・フーガ)がPresenting Partnerとしてタイトルスポンサーを務め、2025年の大会でサポーター向けのギア提供やイベントプロモーションを担っています。 これらの事例は、アジア市場でのアウトドアブランドの台頭を示すもので、トレイルランニングの国際化を後押ししています。
ロードレースの成功事例:TCSのグローバル戦略

トレイルランニングの文脈で参考になるのが、ロードレースでのタイトルスポンサー事例です。インドのTATAグループ傘下のTata Consultancy Services (TCS)は、ニューヨークシティマラソンやロンドンマラソンなどの世界主要マラソンのタイトルスポンサーを務めています。 TCSは現在、World Marathon Majorsの多くをスポンサーし、合計14以上のレースを支援しています。
TCSの取り組みは特に秀逸で、以下のような戦略が見られます:
- VIP招待とネットワーキング:取引先や見込み客を大会に招待し、交流を深める。これにより、B2Bマーケティングを強化。
- テクノロジー活用:TCSの強みであるITを活かし、大会公式アプリを開発。ランナーや家族の応援機能を提供し、ユーザー体験を向上。また、マラソン大会を技術デモンストレーションの場として活用しており、レースアプリでリアルタイム追跡(予測完走時間含む)を提供し、TCSのバックエンド技術(世界の金融取引の4割を支える)を自然にアピール。
- 社会的影響:持続可能性やインクルーシブネスを促進し、経済効果として2.25億ドル以上の地元経済活性化や慈善寄付を実現。
欧米では、マラソンや筋トレなど定期的にワークアウトをしている人は収入が高いと考えられており、企業の役員・VIPなどの意思決定社は日頃から健康に気を使っていると言われている。これらの方々を招待して、TCSだけでなく、顧客同士でネットワーキングをして、Win-Winの関係を構築する。そういった形で、TCSはマラソン大会を通してマーケティングを行っている。
これらの事例から、タイトルスポンサーは単なる資金提供ではなく、企業とイベントのwin-win関係を築くツールであることがわかります。トレイルランニングでも、環境保護やコミュニティ支援をテーマにしたスポンサーシップが増える可能性があります。
まとめ:トレイルランニングの未来とタイトルスポンサー
タイトルスポンサーは、トレイルランニングのプロフェッショナル化とグローバル化を後押しする鍵となりそうです。日本ではまだ少ないですが、京都マラソンのような先駆けがきっかけになるかもしれません。今後、東京マラソンや大阪マラソンといった大都市マラソンが、タイトルスポンサー化を検討していくのではないかと思われる。
また、トレイルランニングの世界においても、今後タイトルスポンサーの獲得が成功の鍵になるのではないかと思う。特に、海外からランナーを誘致するような大規模な国際レースであれば、なおさらで、安全面や質の高い運営をしていくには、不可欠になってくるだろう。
例を上げると、Mt.Fuji100 や Kaga Spa Trail Endurance 100 by UTMB があがるだろう。Kaga Spa by UTMB に関しては、UTMB への加盟金の支払いが大きく財政を圧迫しており、これを解決するにはタイトルスポンサー探しが重要になってくると感じる。台湾でも事例が出てきているので、ぜひ前向きにチャレンジしていただきたい。